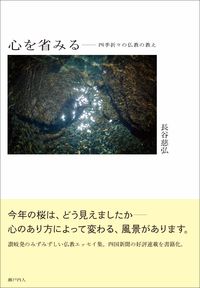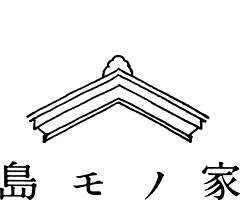- 46版 並製 168ページ
- ¥1760 (本体価格 ¥1600 + 税)
- 2015年07月31日 発売
- 書評掲載情報
- 2015-12-27 読売新聞
評者: 若松英輔(批評家)
紹介
「「少年だよ」雄二はそう返事すると、古川君の肩へ手をかけ、二人は肩に手を組みあわせて歩いた。雨で洗われた礫の路が白く光ってつづいている。遠い世界のはてまで潤歩して行くような気持がした。」(本書より)
「幼少期のこういった記憶を持つ人は少なくないと思う。しかし、原民喜はそれらの情景や会話、心理の細部まで詳細に記憶し、まるでいま目の前で起こっているかのように文章にしてみせるのだ。それも徹底して子供のままの視点で。……そこには、小さく静かな声で語ることでしか伝わらないような、透明な世界が広がっているように感じる。」(田中美穂「解説」より)
遠藤周作や大江健三郎が絶賛した小説「夏の花」の作家が、原爆投下以前の広島の幼年時代を追憶する美しく切ない短編小説集―。広島・被爆70年という歴史の節目に、同地出身の詩人・小説家、原民喜(1905~1951)の文学を紹介。「三田文学」等で活躍し、原爆投下直後の広島の惨状を描いた名作「夏の花」で知られる作家・原民喜。戦後、自ら命を絶つ前に作家自身によって編まれた短編小説の連作「幼年画」をはじめて単行本化。
古書・蟲文庫の店主でエッセイストの田中美穂の解説を付し、原民喜の知られざる初期作品に新しい光をあてる。
前書など
杏の実が熟れる頃、お稲荷さんの祭が近づく。雄二の家の納屋の前の杏は、根元に犬の墓があって、墓のまわりには雑草の森林や、谷や丘があり、公園もあるのだが、杏の実はそこへ墜ちるのだ。猫が来て墓を無視することもある。杏の花は、むかし咲いた。花は桃色で、花は青空に粉を吹いたように咲く。それが実になって眼に見え出すと、むかし咲いた花を雄二は憶い出す。「来年は学校へ行くのだから、今のうちに遊んでおくのよ」と母は云うが、雄二は色鉛筆が欲しいと云って泣いた。大吉の石筆をもらって石に絵を描いたことはあっても、白い紙に色鉛筆でやってみたいのだ。到頭夜遅く、妹の守に連れられて、小学校の前の文房具屋へ買いに行った。帰り路の屋根の色は青く黒く、灯は黄色だった。「夜、色鉛筆使っても駄目よ、黄色なんか白と間違えるから」と姉の菊子は云う。雄二は、しかし、白と間違ってみたかった。……
目次
「幼年画」
貂
蝦獲り
小地獄
不思議
鳳仙花
招魂祭
青写真
白い鯉
朝の礫
「拾遺」
潮干狩り
解説 田中美穂
著者紹介
- 原 民喜
- 1905(明治38)年、広島県広島市に生まれる。少年時代より、次兄と雑誌「ポギー」を発行するなど文学に親しみ、同人誌に詩や散文を寄稿する。18歳で慶応義塾大学文学部予科に入学し、上京。創作活動のかたわら、左翼運動にも関心を深める。その後、同大学の英文科に進学。主任教授は詩人・英文学者の西脇順三郎、卒業論文は「Wordsworth論」だった。28歳で永井貞恵と結婚し、千葉市に転居。1935(昭和10)年、コント集『焔』を自費出版。「三田文学」を中心に作品を発表する。 1944(昭和19)年9月、39歳の時に最愛の妻・貞恵を喪う。太平洋戦争開始後、1945(昭和20)年1月に広島に疎開し、8月6日に原爆被災。戦後ふたたび上京し、慶応義塾商業学校・工業学校夜間部の嘱託英語講師を務め、「三田文学」の編集と創作活動に取り組む。1948(昭和23)年、「夏の花」で第1回水上瀧太郎賞受賞、翌年小説集『夏の花』を能楽書林より刊行。1950(昭和25)年、武蔵野市吉祥寺に転居し、日本ペンクラブ広島の会主催の平和講演会に参加するため帰郷。1951(昭和26)年3月、自ら命を絶つ。享年45。没後、訳書『ガリバー旅行記』および『原民喜詩集』が刊行された。